年末調整
届け出をする
その他
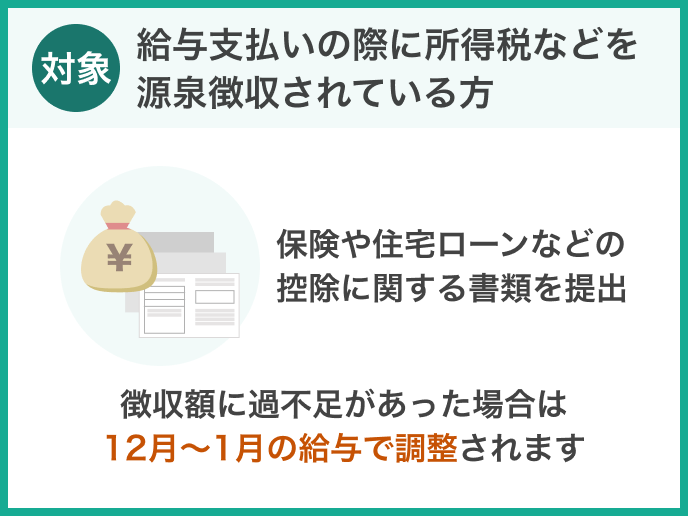
対象となる人
会社員やパート・アルバイトなど、会社などから給与の支払いを受け、所得税などを源泉徴収されている方が対象です。
産休中・育休中の方も、原則、年末調整が必要です。1年の途中から産休や育休に入る場合、年末調整の結果、納税額に払い過ぎがあれば還付金を受け取ることができます。
ダブルワークで副収入が20万円を超える方は、年末調整の他に確定申告が必要です。詳しくは、確定申告 総合ガイドをご確認ください。
内容
目次
1. 年末調整について
2. 2025年の主な変更点
3. 基礎控除
4. 配偶者控除
5. 扶養控除
6. 特定親族特別控除
7. 生命保険料控除
8. 社会保険料控除
9. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
10. 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
11. その他の控除
12. 年末調整対象外の控除
1. 年末調整について
年末調整が必要な理由は、主に以下の2点です。
- 毎月の給与から源泉徴収されている所得税などの合計額と1年間に納めるべき所得税などの合計額を一致させるため
- 配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などを適用するため
年末調整の結果、納税額に払い過ぎがあれば還付金を受け取ることができます。逆に不足があれば、追加徴収される場合もあります。この精算は12月または1月の給与に反映されるのが一般的です。
生命保険料控除や住宅ローン控除などは、支払金額や控除を受けられることを証明する「控除証明書」などを事前に準備する必要があります。
2. 2025年の主な変更点
令和7年度税制改正による主な変更点は以下の通りです。
-
基礎控除額の見直し 合計所得金額に応じて最大95万円の控除(改正前:48万円)
-
給与所得控除の見直し 収入金額190万円以下の場合、給与所得控除の最低保障額55万円→65万円に引き上げ ※収入金額190万円超の場合は変更ありません。
-
扶養親族等の所得要件の改正 扶養親族の合計所得金額48万→58万円以下に引き上げ
-
特定親族特別控除の創設 「特定親族特別控除」の申告が可能
詳細は、国税庁「昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」(PDF)をご確認ください。
3. 基礎控除
合計所得金額に応じて受けられる控除です。(最大95万円)
対象者
合計所得金額が2,500万円以下の人
申請書
「給与所得者の基礎控除申告書」に収入金額などの情報を記入します。
収入金額: 給与や賞与などから税金および社会保険料などが差し引かれる前の金額です。1年間(1月1日~12月31日)の収入合計を記入します。源泉徴収票では「支払金額」の欄が収入金額にあたります。2カ所以上から給与をもらっている場合は、合計額を記入します。
所得金額: 「収入金額」から「給与所得控除額」を差し引いた金額を記入します。給与所得控除額は、収入金額に応じて異なります。基礎控除申告書裏面の【給与所得の金額の計算方法】に収入金額をあてはめて所得金額を計算します。
書き方の詳細は、国税庁「基礎控除申告書」をご確認ください。
4. 配偶者控除
生計を一にする配偶者の収入が一定額以下の場合に受けられる控除です。
対象者
配偶者がいる方で納税者本人の収入と配偶者の収入が下記条件に合致する人
本人の収入条件:合計所得が1,000万円以下(給与収入 1,195万円以下)
配偶者の収入条件:合計所得が58万円以下(給与収入 123万円以下)
※配偶者の合計所得金額が58万円を超えた場合でも、133万円以下の場合は、配偶者特別控除を受けることができます。
申請書
「給与所得者の配偶者控除等申告書」に配偶者の情報や給与所得の金額などを記入します。配偶者控除の額は、基礎控除に記載する納税者本人と配偶者の所得区分をもとに算出します。
書き方の詳細は、国税庁「配偶者控除等申告書」をご確認ください。
5. 扶養控除
配偶者以外の子や親などの扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
対象者
配偶者以外の子や親などの扶養親族がいる人
※対象となる扶養親族は、16歳以上であることや同一生計であること、扶養親族の合計所得金額が58万円以下などの条件があります。
申請書
「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養対象者の情報を記入します。なお、基本情報の記入欄は、控除の有無に関係なく、給与所得者全員が記入します。
書き方の詳細は、国税庁「扶養控除等(異動)申告書」をご確認ください。
6. 特定親族特別控除
対象者
特定親族を有する人
※特定親族とは、給与所得者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下である人です。
申請書
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に特定親族の情報を記入します。
書き方の詳細は、国税庁「特定親族特別控除申告書」をご確認ください。
7. 生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除です。生命保険料控除の合計適用限度額は12万円です。
対象となる保険契約 生命保険:一般的な死亡保険、学資保険など 介護医療保険:医療保険や介護保険など 個人年金保険:「個人年金保険料税制適格特約」の付与条件を満たす契約
対象者
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている人
申請書
「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に、保険会社から届く控除証明書を参考にして、保険会社名、保険の種類などを記入し、合計金額を計算式に当てはめて控除額を計算します。
申請書を提出する際、支払金額や控除を受けられることを証明する控除証明書の添付などが必要です。控除証明書は、加入している保険会社から10月頃に郵便で届くことが一般的です。
書き方の詳細は、国税庁「保険料控除申告書」をご確認ください。
8. 社会保険料控除
社会保険料(健康保険料や介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など)を支払った場合に受けられる控除です。その年に支払った保険料の全額が控除されます。生計を同じくする配偶者やその他の親族の社会保険料も控除の対象です。
対象者
社会保険料を支払っている人
申請書
「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」の欄に、給与から天引きされている社会保険料以外で自身が直接支払った社会保険料の金額などを記入します。国民年金の保険料や国民年金基金の掛金の控除を受ける場合は控除証明書の添付か、提出時の提示が必要です。
書き方の詳細は、国税庁「保険料控除申告書」をご確認ください。
9. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを利用してマイホームを購入・増改築して、一定の要件を満たす場合、住宅ローンの年末残高に応じて受けられる控除です。
住宅借入金等特別控除の詳細は、国税庁「土地・建物(住宅ローン控除等)」をご確認ください。
対象者
住宅ローンの住宅借入金などの年末残高があり、要件を満たす人
※住宅借入金等特別控除を初めて利用する際は、確定申告を行う必要があります。2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
申請書
「住宅借入金等特別控除申告書」に住宅借入金等特別控除額を計算して記入します。
書き方の詳細は、国税庁「住宅借入金等特別控除申告書」をご確認ください。
借入先の金融機関などによっては年末残高証明書の取得方法が変更されている場合があります。詳細は、国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続に関するよくある質問」をご確認ください。
10. 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
小規模企業共済制度の掛金、企業型確定拠出年金(企業型DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)などで支払った掛金の合計金額に対して受けられる控除です。
対象者
小規模企業共済制度などに掛金を支払っている人
申請書
小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)など個人で直接掛金を支払っている場合は、10月~11月頃に届く「掛金払込証明書」をもとに「給与所得者の保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、その年に支払った掛金の合計金額を記入します。
申請書を提出する際は、掛金払込証明書の添付か、提出時の提示が必要です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)などは、勤め先が合計金額を記入するため証明書は不要です。
書き方の詳細は、国税庁「保険料控除申告書」(PDF)をご確認ください。
11. その他の控除
その他に下記控除があります。
12. 年末調整対象外の控除
ふるさと納税などの寄付控除は、年末調整対象外です。確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用することで控除を受けられます。医療費控除なども確定申告が必要です。火災保険の保険料は、年末調整や確定申告の控除の対象外です。